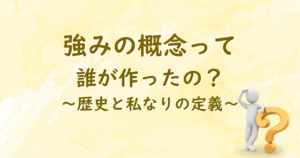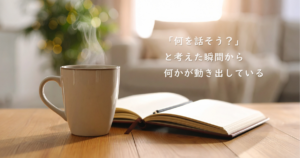「自分の強みを知ろう」
「強みを活かそう」
私はストレングスコーチとして“強み”という言葉をよく使っています。しかし、ふと「強みの概念は誰が作ったのだろう?」と素朴な疑問が湧き上がってきました。
気になって調べてみたところ、強みという概念は、古代ギリシャの哲学から経営学、心理学、そしてポジティブ心理学まで、時代ごとに少しずつ形を変えながら語られてきたことがわかりました。
1. 古代哲学における「強み」:アリストテレス
古代ギリシャの哲学者アリストテレスは『ニコマコス倫理学』の中で、人が生きる目的は「卓越性(アレテー)」を追求することだと説きました。
“The good for man is an activity of the soul in accordance with virtue (arete) in a complete life.”
「人間の善は、魂が理性に従って働く卓越性(アレテー)にある。」
ここで語られる「卓越性(arete)」は、人が持つ資質を最大限に発揮することを指すと解釈できます。それは、特別なスキルではなく、内面的な「優秀さ」や「美徳」として捉えられます。
たとえば
・気づいたら自然に人を笑わせている人
・みんなが迷ったときに、落ち着いて整理して話す人
こうした「ついしてしまうこと」に、その人の卓越性が表れるのかもしれません。
「強み」という言葉は登場しませんが、「自分の特性を活かして生きる」考え方はすでに2000年以上前から語られていたのです。
2. 経営学における「強み」:ピーター・ドラッカー
時代が進み、20世紀、経営学者ピーター・ドラッカーは『現代の経営』(1954)で個人の強みを組織の成果につなげる視点を提示しました。
“The purpose of an organization is to make human strengths productive and human weaknesses irrelevant.”
「組織の目的は、人々の強みを生産的なものにし、弱みを無害なものにすることである」
ドラッカーにとって「強み」とは、成果を生み出すために組織が活用すべき人間の資質でした。
たとえば、職場で「数字に強い人」と「人を励ますのが得意な人」が組めば、片方の弱点を補い合いながら成果を上げられます。
ドラッカーは強みを活かすのが個人の努力だけでなく、組織側の責任でもあることを示唆したのです。
3. 科学的アプローチによる「強み」:Gallup社とドナルド・O・クリフトン
ドラッカーは組織における強みの重要性を説きましたが、個人の強みを科学的に分析し、具体的な能力として定義づけたのが、心理学者ドナルド・O・クリフトンです。彼は『Soar with Your Strengths』(1992)で、弱みに注目する従来の考え方に疑問を投げかけました。
“Don’t waste your life trying to eliminate your weaknesses. Concentrate on your strengths.”
「弱みを克服することに人生を費やしてはならない。強みに集中することが、人間に最も大きな成果と満足をもたらす。」
さらに『Now, Discover Your Strengths』(2001)では、「強み」を次のように定義しています。
- 才能(Talent):“naturally recurring patterns of thought, feeling, or behavior”(自然に繰り返し現れる思考・感情・行動のパターン)
- 強み(Strength):“the ability to consistently provide near-perfect performance in a specific activity”(才能に知識とスキルを投資し、持続的に成果を生む能力)
例えば、「新しいことを知るとワクワクする」という才能に、専門知識や人に分かりやすく伝えるスキルを磨くことで、自分だけでなく周囲の成長にもつながる強みへと育ちます。
このように、クリフトンは才能を強みに育てることこそが、人に最も大きな成果と満足をもたらすと科学的に示したのです。
この考え方をもとに、Gallup社は診断ツール「ストレングスファインダー(現 CliftonStrengths)」を開発しました。
4. ポジティブ心理学における「強み」:セリグマンとピーターソン
強みを科学的に定義し、成果を生む力として確立したクリフトンに対し、心理学に新しい視点を持ち込んだのがマーティン・セリグマンです。
1998年にアメリカ心理学会会長に就任したマーティン・セリグマンは、『Authentic Happiness』(2002)で次のように述べています。
“Psychology is not just the study of weakness and damage; it is also the study of strength and virtue.”
「心理学は人間の病理だけでなく、強みや美徳も研究対象とすべきである。」
セリグマンとクリストファー・ピーターソンは『Character Strengths and Virtues』(2004)を出版し、歴史や文化を超えて共通する24の徳性(キャラクター・ストレングス)を体系化しました。
これが現在の「VIA(Values in Action)」という診断ツールへとつながっています。
ここでの強みは、創造性・勇気・親切心などの、人がよりよく生きるためのものです。
例えば、「友人をさりげなく気づかって声をかける」「失敗しても挑戦を続ける」。こうした日常のふるまいも、立派な強みとされています。
5. 強みの概念は「進化」してきた
強みの概念は、このように時代や分野の流れの中で少しずつ形を変えながら提唱され、発展してきました。
そして、「強み」という言葉の定義は、分野によってニュアンスが少し異なります。
| 時代・人物 | 強み | 分野 |
|---|---|---|
| アリストテレス(紀元前384–322) | 卓越性(arete)=資質を最大限に発揮すること | 哲学 |
| ドラッカー(1909–2005) | 成果を生むために組織が活用すべき資質 | 経営学 |
| クリフトン(1924–2003) | 才能×(知識+スキル)→成果を生む能力 | 心理学/Gallup |
| セリグマン(1942 –存命)& ピーターソン(1950– 2012年) | 文化を超えて共通する24の徳性→よりよく生きるための基盤 | ポジティブ心理学 |
時代とともに、「強み」は 個人の特性 → 組織の資源 → 成果を生む力 → より良く生きるための基盤 へと広がりを見せてきました。
他にも教育や福祉、組織開発など他の分野でも「強み」は語られてきていますが、現在コーチングや自己理解の場面で広く使われている“強み”の考え方に特に大きな影響を与えているのはこの4人だと思います。
6. 私の「強み」の定義
こうして歴史を辿ってみると、「強み」という言葉には多様な意味が込められていることがわかります。では、私自身にとっての「強み」とは何か?
私自身がいま一番しっくりくる定義は
「自然にできて、エネルギーが湧き、自分そして周囲に対してよい影響を与える力」
です。
この定義には、大切な3つの要素が含まれています。
- 『自然にできること』:無理な努力を必要とせず、当たり前のように、努力感なく発揮されていること。
- 『エネルギーが湧くこと』:やっていて疲れるのではなく、むしろ活力が生まれ、集中力や生産性(パフォーマンス)が向上する感覚があること。
- 『よい影響を与えること』:自分自身の成長や充足感、そしてより豊かな人生につながるだけでなく、周囲の人にもよい結果や変化をもたらすこと。
つまり、自分らしさが発揮されていて、やっていて満たされる。そしてその力が巡り巡って、周囲の人にもよい影響を与えるとき、それは確かな「強み」と呼べるのではないでしょうか。
Enabby Coaching の「ストレングス・インテグレーション・プログラム(全5回)」では、この定義を土台に、あなた自身が強みを丁寧に言語化し、日常や仕事での活かし方を見つけていけるよう伴走します。

参考文献
- Aristotle. Nicomachean Ethics.(アリストテレス『ニコマコス倫理学』)
- Drucker, P. F. (1954). The practice of management. Harper & Row.
- Clifton, D. O., & Nelson, P. (1992). Soar with your strengths. Delacorte Press.
- Buckingham, M., & Clifton, D. O. (2001). Now, discover your strengths. Free Press.
- Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Free Press.
- Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. Oxford University Press.